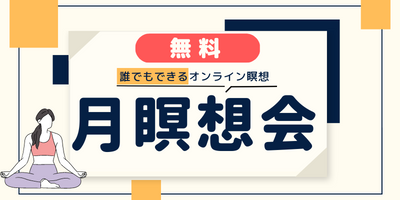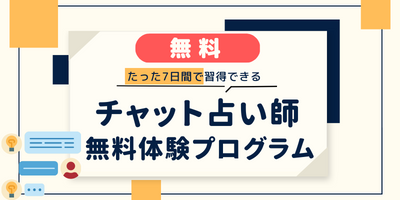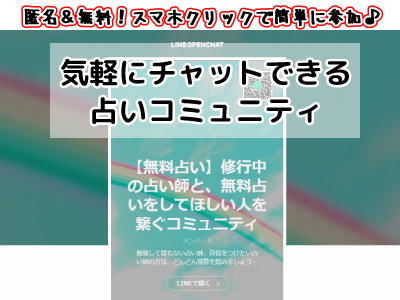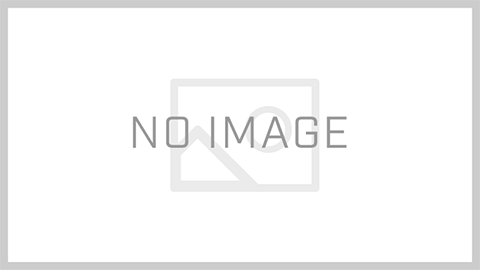占い好きの友人と話していると、必ずといっていいほど出てくる疑問が「算命学と四柱推命、結局どちらが当たるの?」です。
どちらも生年月日(四柱推命ではプラス出生時刻)から運命を読み解く“命術”ですが、ルーツや理論が異なるため、見えてくる世界も少しずつ違います。
ここでは両者の特徴と得意分野を丁寧に比べながら、「あなたに合うのはどちらか」を一緒に探ってみましょう。
1 算命学とは
算命学は、中国の戦国時代に芽生えた思想をもとに、日本で独自に発展した占術です。
陰陽五行をベースに「十大主星」や「十二大従星」などを配置し、人生のテーマや宿命の役割を読み取ります。
-
宿命と環境の“ズレ”を発見しやすい
-
家系や社会との関わりを立体的に捉えられる
-
自分の「役割意識」を深く掘り下げるのが得意
たとえるなら、算命学は“人生の設計図”を俯瞰で眺め、「自分はどんな建物を建てるために生まれてきたのか」を教えてくれるイメージです。
2 四柱推命とは
四柱推命は、中国で体系化され、現在も東アジア圏で最もポピュラーな命術の一つです。
生年月日と出生時刻から「年柱・月柱・日柱・時柱」を出し、十干十二支の組み合わせで運勢を推測します。
-
大運・流年など“時期読み”に強い
-
性格・健康・金運など多角的な分析が可能
-
流派が多く、研究を重ねるほど奥深い
こちらは“人生の潮流”を精密に測り、いつ追い風が吹くか、いつ凪になるかを教えてくれる高性能な潮汐カレンダーのような存在です。
3 「当たる」とは何を指すのか
「当たる」という言葉には二つの側面があります。
1つ目は“的中率”という事実的な精度。2つ目は“納得感”という主観的な満足度です。
どちらの占術も理論が緻密なため、的中率は占い師の経験と解釈力に左右されます。
一方で納得感は「知りたいテーマ」と「占術の得意分野」が一致しているほど高くなる傾向があります。
ですから、どちらが優れているかを決めるより、「今の自分が何を知りたいか」で選ぶほうが、結果的に“当たった感”を得やすいのです。
4 相談内容別・おすすめ早見
| 知りたいこと | 算命学で見るメリット | 四柱推命で見るメリット |
|---|---|---|
| 自分の本質や適職を深く知りたい | 宿命の役割が立体的にわかる | 性格・才能を細かく分類できる |
| 家族関係やパートナーシップ | 家系図的に関係性を整理できる | 二人の運気の波を時期で照合できる |
| 転職や独立のタイミング | 宿命の使命と現状のギャップを確認 | 大運と流年で“勝ち月”を特定 |
| 今年・来月の運勢 | 宿命×年運のバランスを俯瞰 | 流年・流月でピンポイント予測 |
5 選び方のコツ
1 目的をはっきりさせる
「人生の設計図を知りたい」のか「目の前の選択をベストにしたい」のかで適した占術は変わります。
2 占い師との相性を重視する
同じ占術でも、解釈の深さや語り口は人それぞれ。信頼できる人を選ぶことが“当たる体験”への近道です。
3 両方受けてみる
少し贅沢ですが、算命学で宿命を俯瞰し、四柱推命で時期を具体化すると、立体感のある人生戦略図が完成します。
6 天中殺は2年か3年か
1.まずは結論ざっくり
| 占術 | 代表的な年数 | 根拠となる考え方 | よく混同される派生・流派 |
|---|---|---|---|
| 算命学 | 2年 | 12支のうち“欠ける”2支が連続するため | 特になし |
| 四柱推命 | 2年が古典的。標準 3年とする流派も存在 |
本来は「空亡=六つの2支セット」→2年 細木数子氏の六星占術ほかは“前厄・本厄・後厄”で3年 |
六星占術の大殺界(3年)、子宮推命など |
ひと言まとめ
-
教科書どおりの四柱推命&算命学ならどちらも 2年。
-
「3年説」は六星占術など独自改編がルーツ。
- 私の学んだ算命学では、年運の天中殺は「天中殺の年に入った瞬間に切り替わる」というよりも、前後半年をかけて少しずつ天中殺の影響に移行していくと教わりました。
そのため、実際の体感としては「2年間+前後半年」、つまりおよそ3年間が天中殺期にあたると捉えています。
2.どうして年数が変わるの?
-
計算ユニットの違い
-
古典的四柱推命・算命学とも「十二支を2支ずつ欠けさせる」という同じ公式を採用 → 2年。
-
-
日本ローカライズの“+α”
-
細木数子氏が“四柱推命ベース+独自命名”で広めた六星占術は、厄年の考え方を取り入れ「前後を含め3年」に拡張。これがメディアで圧倒的に有名になり「四柱推命=3年」と誤認されやすい。
-
-
3.天中殺の“長さ”より大切な視点
チェックポイント なぜ大事? ワンポイントアドバイス ① どの階層を見ている?
(年・月・大運)同じ占術でも階層が違えば期間も違う 相談内容に合ったレイヤーか必ず確認 ② 流派のアルゴリズム 独自アレンジで年数が+1される事も 公式サイトや占い師に「何年で取る派ですか?」と聞く ③ “避ける”より“活かす” 天中殺は“人生の夜”=充電モード ・受け身でインプット強化
・無理に形にしない
・人に頼る練習期間と考える☕ 豆知識で和みタイム
十二支を“動物”で覚えていると、欠ける2支が うちの干支じゃなかったラッキー! とか言いたくなりますが、実際は全員に必ずやって来ます。 「夜が来ない国はない」のと同じで、“当たり前に来る夜をどう眠るか”が勝負です。結局のところ
-
理論の原点に立ち返れば、四柱推命も算命学も「年運天中殺=2年」がスタンダード。
-
3年説はメディアで有名な派生法則(六星占術など)が広めた“厄年ミックス版”。
-
期間の長短より、どの層で何を整えるかを意識した方が実践的。
「夜が来たら睡眠にフォーカス」するのと同じように、天中殺は“内省・学習・点検”にフォーカスする時期。
期間の数字に振り回されず、自分のアップデートタイムとして賢く使っていきましょう。
-
まとめ
算命学を柱に、四柱推命も少しかじっている私の実感としては、両者に決定的な差があるとは思いません。
最大の違いは「出生時間を使うかどうか」くらいで、深く掘り下げれば下げるほど、流派ごとに解釈や用語が変わるのが実情です。
算命学にはいくつかの大きな流派があり、高尾学館や朱学院でも、それぞれ教え方や重視するポイントが異なります。
それぞれの流派で学ばれた方とお話しする機会もありましたが、細かい部分に踏み込むと、解釈や表現が少しずつ違うのです。
私は研究者ではないので、そこまで細部を網羅するより、実践で役立つポイントを押さえるほうが大切だと感じています。
「当たる」と思えるかどうかは、占い師の視点や語り口に左右される部分が大きいでしょう。
算命学がしっくり来るなら算命学を、四柱推命が腑に落ちるなら四柱推命を信頼すればいいのです。
なお、私自身は、それぞれの長所を組み合わせて鑑定しています。
今のあなたが知りたいテーマに最もフィットする占術を選び、信頼できる占い師に相談してみてください。きっと必要なヒントが、最良のタイミングで届くはずです。
この占い師さんに相談したい!という直感を大事にしていただき、ぜひ占いを受けてみてくださいね。